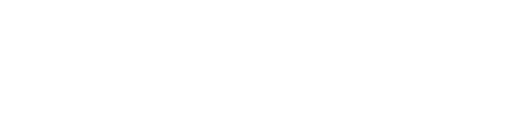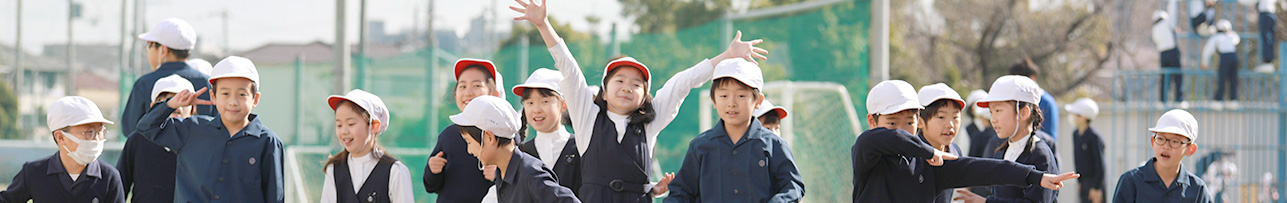お知らせ
2025/07/04
横山 知子 教諭(左)
2年A組担任 学年主任 図書科
森本 浩美 教諭(右)
1年A組担任 学年主任 国語科
国語教育や読書教育に力を注ぐようになったきっかけ
森本 もともとは、図書担当でもなく普通に担任をしていました。実は図書に特化していたわけではなかったんです。「賢明で図書の担当をしてほしい。」というお話があって、賢明に来ました。では、なぜ図書にこれだけ力を入れるようになったかというと、賢明に来て最初に出会ったシスター藤井先生との出会いがきっかけです。藤井先生は創立当初から図書館教育にとても力を入れてくださり、「学校というのは図書館を中心として考えたらいい。」とおっしゃる程、本による子どもたちの成長への力が大きいものだと私に教えて下さいました。それは特別に難しい話をされたわけではなく、私が子どもたちと図書館で関わっている中で、「先生こういう時には、こんな本を勧めたらいいよ!」とか「この本を読んで、私はこんな風に変わったよ!」とか、子どもたちに指導する上で本に関わることがどれだけ大切かを毎日のように自然と教えてくださいました。徐々に本の大切さを感じるようになり、夏休みを使って司書教諭の資格も取りました。ですから、賢明に来たおかげで素敵な出会いを頂けたと思っています。
司会 司書教諭を賢明に来てからとられたのは知らなかったです。
森本 数年かけてとりました。それくらい大切だと思ったので、子どもたちにその大切さを伝えています。
横山 私は自分が小さい時から本を読むことが好きで、当時は夏休みになったら、することがなかった時に、午前は図書館に毎日通って、午後はプールに行っていました。毎日図書館で本を借りて家で読む生活を過ごしていました。小さいころはなりたいものが色々あったんですが、大学で進路選択をするときに、小学校の時の先生がとても熱心に子どもに関わってくれて、そこから学校の先生になりたいと思いました。また、その頃から国語の先生になりたかったから国語専攻で、卒業論文も国語や図書指導の研究をしました。教育実習に行って絶対小学校の先生が良いと思い、それから賢明にお世話になることになりました。
赴任当初は1クラス44人で88人をもつことになりました。文集や石ころを88人分する、日記を毎日読む、そうして子どもたちと向き合い、子どもたちの文章と向き合う毎日で、いっしょに読んだり、書いたるする中で国語や読書教育の大切なことがたくさんあると感じました。
ずっと国語を担当してきたので、子どもたちの感性の豊かさとか、特に文学的文章だと同じ教材を読んでも20年前の子どもたちの読みとちがった新しい発見が今でもあり、奥が深いと思っています。
司会 僕は本を読んできた中で、森本先生からは原田マハさんの『本日はお日柄もよく』を、横山先生からは『僕はブルーでホワイトでちょっとイエロー』を紹介していただきました。保護者の方や児童、先生方にもたくさん紹介されていると思うのですが、どういった決め手で紹介しているのですか?
横山 自分が好きな本のエッセンスでお勧めします。自分がその本を読んでいいなと思わないとお勧めできないと思うので、自分が好きなものを紹介します。そして、その人を思い浮かべます。例えば森内先生だったら、料理が好きだから、お弁当にまつわる本なんていいかなと。今では高学年から低学年に変わって、子どもたちの興味や読める本のレベルが違うので、目の前にいる子どもたちがいいなとか楽しいなと思う本を勧めています。
司会 自分が好きになるってとても大切ですよね。
森本 自分が読んでいていいなと思うと同時に「この話きっとあの人喜ぶだろうな。」とか「興味あるだろうな。」とか思い浮かんできます。それは相手が先生の時もあるし、子どもの時もあります。その子の顔が浮かんできますね。絵本の紹介で、低学年の子どもで友達のことについて学んでほしいことがあったら、「あの子今こんなことで悩んでいるからこの本を読んでちょっと救われるんじゃないか。」とか、普段からいろんな子どもと付き合いがないと浮かばないんです。だから、この仕事
をしている以上、いろんなタイプの子どもと出会って、とにかくたくさん接することでその人の顔が思い浮かぶんだと思うんです。いろんな人に対する思いがあっても、その人のことをどう解釈するべきかを考えていくことが大切だと思っています。
時代が変わっても変わらない賢明の国語教育
森本 国語科の教科目標である「自分の思いを表現できる児童」これにつきます。これはずっと変わっていません。図書でも一緒で私たちが目指している子ども像はそこかなと思います。時代がどう変わっていっても自分の思いは自分でしか話ができないので、それをきちんと言葉で表すことができるか。その表し方が文章であろうと詩であろうと俳句であろうと作文であろうと感想文であろうと、作り方もタブレットを使って入力するだけでなく自分で書くことも必要です。どんな形でもいいから自分の言葉で表現することは、ずっと変わりません。これからも変わらないと思います。
横山 今年は「自分らしさ」がピックアップされているけれど、それを見つけるために何が必要なのかを見つける過程で、やっぱり温故知新の部分があります。古きを訪ねていろんなアプローチをすることが大切です。賢明学院小学校の子どもたちが、宮沢賢治さんの作品を読んで、その文章やその人となりから何を学んで、何を自分らしさの中に取り入れていくか、また、20年前と現在の違いが何かを考えていく必要がある。そこが自分らしさを見つけて表現するというところつながると思います。今は算数も教えていてオープンアプローチのように自分の問いを持って、一人ひとりの問いを活かした学習過程を作っていくことが大切だと考えています。
今と未来を生きる子どもたちを育む賢明の国語教育
森本 アプローチの仕方がもっともっと多種多様になっていくと思います。そこでいかに色んなアプローチを身に着けていくかがさらに大切になっていきます。AIなどが普及しているからこそ、さらに広がっていきます。それを知ることや自分なりに使いこなせることが必要になってきます。私たちが子どもの時は携帯電話がなかったですが、今となっては考えられません。今や携帯電話がないと生きていけない生活を送っています。そんなことが気にならない程のものをこれからの子どもたちは身につけていくことになると思います。でもそれを身に着けるためには、そういう時代になったからこそ自分の考えを持つことや自分の考えを持つことがとても大切になってきます。そこには、その時代ごとの価値観が入ってきます。同じ本を読んでも、数十年前の子どもたちと今の子どもたちでは思うところが違ってきます。それは、常にその人の本の読み方があるからです。同じように今後を生きる子どもたちの価値観はその人にしかないものであって、その価値観をしっかり持てるかが問われてくると思うんです。そのために賢明の今までの国語教育をずっと大切にしていかなければならないし、受け継いでいかなければなりません。だからこそ、読書感想文コンクールであったり、毎年一回発行の石ころはずっとずっと続けていくべきだと思っています。
横山 「石ころ」についてですが、作品の文集を出している学校はあるけど、結局一つの単元について全員載せたり、選ばれた人だけとかが多いです。でも石ころは全員。一人一作品を、自分の言葉で紡いでいくところに価値があります。卒業生の子が入学して、自分の親の作品が載っているのを見て、「僕もこう思うな。」とかそういうのは素敵だと思います。昔は問いを与えられて、それに対する考えや答えとかを考える学習が多かったけど、今では問いを自分で見つけてそれを解決していく学習が多いし、実際問いに対する答えはAIが解決してくれる時代になってきたので、クラスの中で共感したり、自分や他者の感情を理解したり、それを自分の言葉で創造してくことが小学校の学びの中で大切だと思います。
例えば、スイミーはずっと教科書に載っているけど、スイミーの好きな場面を聞くとだいたい、いろんな海の生き物が出てきてスイミーが元気を取り戻す場面とか、最後に大きな魚の姿になって追い出す場面が多いです。そんな中で、はじめの一場面のところが好きな子がいました。なぜか聞いてみると「兄弟で仲良くしているところがそこしかないから。」というんですね。その子なりの感性をクラスの中で共感したり、なるほどって思うのは昔も今も変わらないです。アプローチの仕方が色々変わっても自分の言葉や思いを持って次につなげていくことは国語の大切さが詰まっています。私たちが季節のものに心を動かしたり、自然に触れたりすることを通して、生活の中からも言語環境を整えていくことはこれからも大切になってくると思います。
森本 いろんなものが発達してきて、とても便利なものが増えてきたけれど、それによって逆に不安になることもあります。そうならないように、自分が何を大切にするべきなのかを持っておく必要があると思います。例えば子どもたちが宿題をしている時に、「こんな大きな字、
書くことないやん!大人になってこんな大きな字書かないやん。なのになんでやらなあかんの?」と低学年は言ってくることがあると、保護者の方から聞きます。お母さんは「宿題やからやらなかんやん。」としか言えないです。字も書くのが面倒くさい時もあるけど、そこをきれいになぞって書けるようにゆっくり忍耐強く書く力、これは非認知能力であって目には見えないけれど、大人になったときに何か壁にぶつかっても忍耐強く受け入れることができることにつながります。苦手なことがあってもそれになんとか向かって頑張っていこうと思える、そういう気持ちを幼い時から育てていかないといけないと思っています。そのために本校では、国語辞典を使って1ページ1ページめくりながら言葉を探したり、読書感想文という何度も推敲しながら文章を良くしていくことをしてきているので、その大切さは便利なものを取り入れながらもずっとやっていくことだと思っています。
横山 学年集会でもいつも良い習慣をつけるって小学校の時が大事だと伝えています。良い習慣は積み重ねないとなかなか身につかないけど、小学校でついたら一生物です。習慣は才能を超えます。逆に悪い習慣はすぐについてしまいます。やっぱり丁寧な文字って、見るだけでその人を表すような感じにもなるし、きちんと文字を整えて書くというのは、身につくものが多いと感じています。小学校だからこそ、削ったらダメなものもあって、実体験に基づく感覚も大切にしてほしいですね。