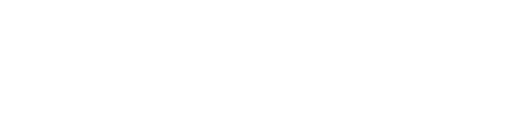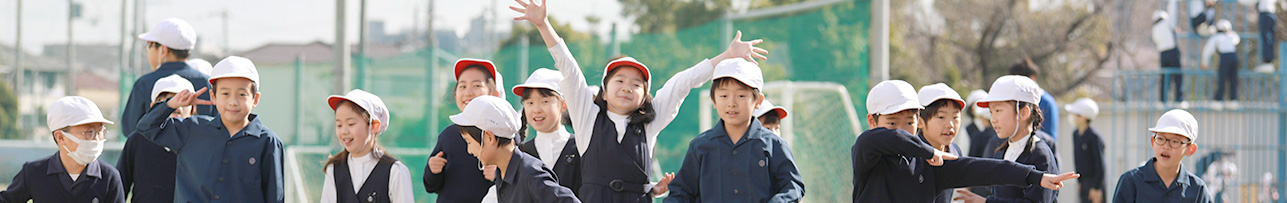お知らせ
2025/07/18
安達 貞夫 教頭
奈良 歩 教頭補佐
教師になろうと思ったきっかけ
奈良 実は最初は先生になるつもりはありませんでした。大学で心理学の勉強をしたいと思っていたんですね。高校生の時に少年犯罪が社会的に問題になっていたことがきっかけで、少年犯罪に関わる仕事を考え、発達心理の学部に進学しました。その中で、事件の加害者となった、少年の生い立ちや事件の詳細の文献を見て、「家庭環境や集団への適性に問題があり、学校の中で居場所がないまま大きくなっていった」というようなケースをたくさん知りました。生まれてくる家庭は選ぶことはできないからこそ、社会の中で、大人がもう少し何かしらの手を差し伸べていたら、違った運命があったのではないかと思いました。事件が起こってからの手立てよりも、起こる前にもう少し人生が変わるような手立てや軌道修正をしてあげて、子どもたちに豊かな人生を歩んでほしい思いから教師になりました。
安達 とても崇高ですね! 私は小学校の時に『兎の眼』を読んだことが、きっかけでした。主人公の小谷先生を陰ながら応援している少しやんちゃな「足立先生」にあこがれて、こんな先生になれたらと思ったのが最初のきっかけでした。そして、自分自身が4年生で転校した先の小学校や中学校は少し落ちつかない学校だったのですが、中学校の時に出会ったとても影響力のある先生に魅力を感じたのが、次のきっかけです。高校に進学した時にとても一体感のある教師集団に出会い、この一員になりたい思いが生まれ、高校教師になりたいと、高校社会教員免許を取れる大学に進学して教師の道を考え始めました。当時は競争率も高く難しかったのですが、教育に関わりたい思いが強く残り、民間教育の世界に行きました。自然活動やキャンプも実施しているような進学塾に就職、二社を渡り歩いたあとの企業で、法人事業部門に移り、学校と関わることが増えました。学校の先生の良さを改めて肌で感じ、「小学生の可能性」に気づいたこともあり、小学校教員免許を44歳で取得しました。当時息子たちが受験の時期で資金に余裕なく、借金して通信制大学に出願したのですが、逆に過去ないくらい必死に勉強しましたね。賢明学院に来た当初は、まだ小学校免許がなく高校教師でしたが、高校1年担任や海外研修引率などの経験を経て小学校に来ました。
奈良 小学校にきてどうですか?
安達 思ってもみなかったのですが、とてもいい経験をさせてもらっています。自分が以前担任をしていた高校生が、小学校運動場に来て、その時の担任の5年生たちと一緒に遊んでいる姿を見て、とても嬉しかったのを今でも覚えています。
司会 二人とも、もともとは小学校の先生は考えていなかったんですね。びっくりです。
昔と今の教育の違いから考えること
奈良 今の子たちは自分で勉強を進めていかないといけないのが大変だと思います。与えられていることだけをやっていくだけでは足りないし、時間も少ないと思います。厳しくする、ということのあり方も時代の変化に伴って変わっており、大人から強制することも限られているから、自分で学習などを進めるしかないのが今の子どもたちには大変じゃないかなと思います。
安達 納得して自分からしようとしない限り大変ですよね。
奈良 大人からは、子どもに無理やりさせることは難しいので、自分で決めて行動に移していくことが今の子どもたちには大切だと思います。
安達 逆に納得したら行動に移す子は多いですよね。そういう意味では、いい方向に変わっていると思います。
教育が変わってきているというよりも社会が変わってきていますから。
奈良 今の子は自分の「スペックを上げていく」というよりも、自分を「乗りこなす」ということが必要と感じます。「自分はこんな人間で、こういうことは得意だけど、こういうことは不得意だ。」と自分を理解して、自身を発信していくことが求められているように感じます。ひたすら学力を上げるのではなく、自分自身をより深く理解して、生きていく力が求められるのではと思います。
安達 ICTが入って、一人一台のタブレットが導入されてから、一人ひとりが自分に合った学びをできるようになってきました。だからこそ、全員が同じことばかりをする必要はないのではないと思います。それぞれが、自分に合ったやり方で、学びたいことを追究していくことも大切です。ただ、学校としては正直やりにくいところもありますね。難しいけれど、こういう方向性にシフトする必要があります。
司会 僕は平成生まれなのですが、昭和や平成の子どもたちの方が生きる力があるんじゃないかなと思ったりもします。今は便利すぎる分、それに全部頼ってしまい、考える力が衰えているようにも感じるんですね。昔は何かトラブルがあっても、とにかく今あるものでどうにかしようとする力が必然的に備わってたんじゃないかと思っていました。
安達 それは考え方であって、今の時代はICTがあるからこそ、それを使いこなす力が大切です。ただ昔の教育だと子どもの数も多かったので、おいてきぼりになる子はいたと思います。バブルがはじけて、チャンスをものにできなかった人もたくさんいました。だからこそ今の子たちの方が、チャンスがたくさんあると思います。
奈良 例えば、昔は都会に住んでいなければなかなかチャンスをつかむことが難しいこともありました。でも今は、例えば音楽でも自分なりの表現をYouTubeなどを通じて世界に発信することもできますし、今の人たちは上手に利用することで、自分の力で活躍の場を広げることができていると思います。難しいなと思うことは、昔は教師側から与える情報が全てでしたが、今では児童もその気になれば、教えようとする知識などについてはいくらでも自分で調べることができます。知識に関しては書籍やテレビ、動画教材などで自分で学べますし、例えば逆上がりにしても動画教材があって自分で学ぶことができます。だからこそ、「教師は何を教えるか」を問われます。いろいろな要素が必要になってきていますよね。
司会 今では、ティーチングよりもコーチングやサポーティングなど、児童が主体に変わって、教師の立場はコーディネートする側になっていますよね。
今の子どもたちが求められる能力
司会 2030年に教育改革がされる中で、先を見据えて先進的に教育を進めていかないといけません。だからこそ、先生方が思う将来求められる能力ってどんな力でしょうか。
奈良 先ほども言ったように「自分を乗りこなして発信していく力」だと思います。私の経験ですが、体育大会の団体種目で、その競技が苦手な子がいて、その子のせいで負けそうになると、本人も気まずい思いをやる気のない態度に出したりして、みんながいやな気持ちになる、というような場面が時々あります。その中で、一度「僕は苦手だから、みんなの足を引っ張りそうで怖いんです。」と私に伝えて来た児童がいましたので、「ではそれをみんなに言ってみましょうよ!」と伝えました。そしてその子は、みんなの前で「僕は台風の目が苦手だから、みんなの足を引っ張ることが不安です。」と言いました。するとクラスのみんなは「大丈夫だよ!みんなで頑張ろうよ!」と言っていたんですね。同じ様に苦手でも、なんだか分からないけどやる気のない様子でいられると周りは厳しく当たりますが、「僕は苦手なんだ。だから助けてほしい!」としっかり自分の思いを発信すると、周りは「助けたい、力になりたい」と言う気持ちが生まれます。この先どんな時代がきても、自分がどういう人間でどういう風に表現したいいかとか、どういう風に助けを求めたらいいかとかを分かっていると、先の見えない世の中だからこそ、自分を守る手立てにもなると思っています。
安達 具体的に言うと、自分をしっかり見つめなおすことができるかと、それをしっかり表現できる能力が必要になってくるということですよね。埋もれていてはだめだし、自分から主張をすることも大切。でもここで難しいのが「では、主張できなかったらその人はだめか?」となるとそうでもないと思います。コツコツと地道に努力し続ける子もいるからこそ、みんながそれぞれ違った
場面での活躍する場が必要になってきます。賢明では田植え体験や様々な宿泊研修等、低学年では畑仕事を毎日行っています。様々な学習体験の中で、自分の活躍できる場をたくさん見つけて、自信につなげてほしいと思います。さらには、仕事も大きく変化してきていますので、自分に合った仕事を自分で決められるように模索していく力をつけてほしいですね。キャリア教育は早期からすることはとても重要だと思います。
奈良 職業に対する価値観も考え直していかないといけないと思います。良い大学に入って銀行員だからいいとか大手の商社マンだからいいというのはなくなってきて、今では若い人でも化粧品のプロデュースなどを自分でして活躍している人いますもんね。
安達 先見的な目を持つことが今の子どもたちに必要になってくるのではと思います。結局は、子どもたちが社会で活躍できるように今教育を行っていますからね。
学年・学級経営で大切にしていること
安達 とにかく子どもたちを観察することを大切にしていました。やはり、子どもたちが今どんな様子なのかを把握しておかないと、子どもたちの成長のための次の一手が打てないです。だからこそ、子どもたちと一緒に遊んだりして、子どもたちの様子を近くで見ながら支えていました。あえて、全部を言うことはせずに、自分たちで考えさせることは意識していました。
奈良 本当は集団をまとめたり上手に動かしたりすることは少し苦手だと思っていましたが、自分が一貫して貫いてきたことはあります。それは「周りから味方されないような人にこそ、自分は味方でいよう」とすることです。私が教師になろうと思ったきっかけの根底はこの部分にあるため、それは心がけています。
賢明には、たくさんの個性豊かな先生方がいますので、必ず誰かが6年間の小学校生活の中でいろいろな先生と出会う中で各々のタイミングで成長していくからこそ、私はうまくできないところは他の先生にゆだねて、できることを貫いてきました。
管理職から見る賢明学院小学校の良さ
奈良 子どもの見取りが本当に熱心です。この子はこういう性格だとか、この子にはこういうことにチャレンジさせてみようとか、それぞれの子どもの可能性や課題も含めて、担任だけでなくいろんな教科の先生方が理解しています。そして、その子に対してあらゆる手を使って、可能性をさらに引き出し課題を克服できるようにサポートしています。声掛けや指導の仕方を含めて、宿題の出し方や問いかけ方などを、的確に判断して対応しているところが一番の良さだと思っています。
安達 帰り道に何らかのトラブル(電車の遅延やダイヤの乱れ等)があったときには、全員の子どもたちが無事に帰宅するまで、先生方は誰も帰宅しないんですよね。当たり前に。全力で対応する姿が当たり前のようで当たり前ではない素敵なところだと思います。人身事故で電車が止まった時に、鳳駅のホーム内まですぐに対応しに行く先生や上野芝駅、駅までの道などに瞬時に判断して各自が動き出す判断力と臨機応変さはすごいと思います。
司会 何よりも子ども思いですよね。体育大会の準備や音楽会の準備など子どもためとなれば、みんなで一致団結するときの勢いは本当にすごいと思います。
奈良 賢明の先生って、どの子にも絶対に声かけますよね。自分の担任じゃなくても通りすがりとかに会ったら、みんな声をかけていますよね。バッテリーを借りに職員室にきて待っているときには、「最近どう?」という風に、みんなに声を掛けます。どの子に対してもその子に対する素敵な情報を持っていて、「頑張っているね!」とか「よく頑張ったね!」というように声をかけて、みんなでみんなの成長を見守るところがあります。
授業についてもチャレンジ精神を持っていますよね。授業についても去年のままとかではなく、必ず何か新しいことにチャレンジして授業に臨む姿があります。
賢明学院小学校の未来
安達 世の中が変わってきて、何が理想かも変わってきている中で、今までしてこなかったことにチャレンジすることは絶対条件ですよね。この学校はそもそもフランスで生まれたグローバルな学校だからこそ、真の国際教育を目指していかないといけないと思います。要するに世界的な学校です。
奈良 私立小学校はイズムが必ずありますよね。公立の場合は、その時の担任の先生や学年のカラーに染まることはありますが、その小学校のイズム的なものが身につくということは自分の経験上思いにくいです。賢明のイズムをこれからもずっと大切にしていき、ここで学んだことを世のため人のために使う使命感を持って帰属意識を持てる学校で在りたいです。幼稚園から高校までの15年間で、どんな世の中になろうとも絶対に迷わず歩み続ける賢明イズムを身につけていってほしいです。
安達 マリーリヴィエ様の「あなたのできるよいことはなんでもしなさい」をこれからもずっと大切にしていきたいですし、ずっと受け継がれているのが賢明学院のいいところですよね。賢明の教育理念が今の自分を作り上げたといえるようなものであってほしいです。
安達 貞夫 教頭
京阪地区、大阪市内、南大阪の民間教育企業進学塾部門で社会科講師、校舎長、エリア長を勤めたあと,本社法人事業部長、幼児教育部長、英語教育事業部長を務める。高等学校公民科・地歴科教諭として賢明学院に移り、その後社会科専科として小学校へ異動。2014年4月より教頭補佐着任とともに、主に高学年担任も務める。2024年4月より教頭着任。
奈良 歩 教頭補佐
神戸大学卒業後、神戸大学附属明石小学校を経て賢明学院小学校へ赴任。理科、図工等専科担当を経て、担任、学年主任など児童と直接かかわる現場にて20年以上のキャリアを持つ。2024年4月より教頭補佐に着任し、主に教務関係と入試問題作問、課外教育と保健主事を担当。2025年4月からは広報、入試作問、課外教育と保健主事担当。