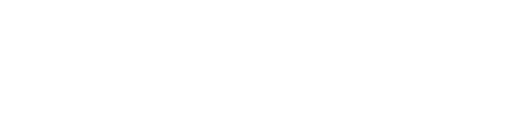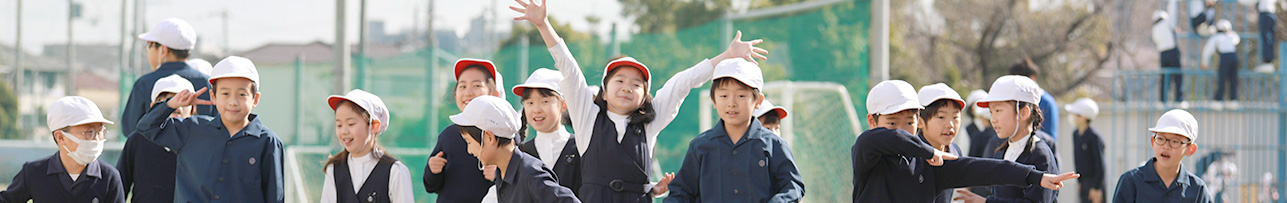お知らせ
2025/08/09
第5回トークセッションは英語科教員によるお話です。

中村 直紀 教諭
関西外国語大学、 アリゾナ州立大学にて実践的な英語教育指導法を学び、 ECC外語学院で講師、 統括部長等を歴任した後、 賢明学院へ。 中高を経て、 現在小学校英語科主任。 現在、 文部科学省「AI の活用による英語教育強化事業」 実践において、プロジェクトのリーダーとして取り組んでいる。

反田 任 教諭
公立中学校を経て、 長く同志社中学校英語科教諭として勤務。 ICT教育にも早くから取り組み、Apple Professional Learning Specialist、Apple Distinguished Educator 等の資格も取得。 瀬戸SOLAN学園初等部を経て、 2025年4月より本校英語科教諭に着任

英語科やICTに専門性を持つようになったきっかけ
反田 英語の授業がとても面白いと感じたのが中学3年生の授業でした。課題は多かったですけど、英語の文章を理解することだけでなく、表現方法や時代背景・社会背景まで調べる課題が結構出ていました。あとは英語の詩を学ぶときにリズムの面白さが授業の中で学習して、結構面白かったんですね。実は英語の成績は中学の時は、そこまで良くはなかったんですけど、英語という教科は好きでした。そして高校に入って、一から英語の勉強をし直しました。自分自身が英語は好きだったけど、成績は普通だったので、英語がわからない子どもたちがいたらその子たちをヘルプできる立場っていうのは、先生しかないと思ったんです。その後、同志社大学の英文学科に進み、最終的には英語の教師になりました。
ICTに関しては、もともと新しいもの好きで、Windows95が出たときにネットワークの構築を学校でしていました。その時は、インターネットを導入する学校はまだ少なかったですけど、一人一台で40台のノートパソコンを導入して授業ができる環境に整えました。ただキャンパスの移転に伴い、もう一度Wi-Fiの設計などを行うことになりまして、iPadの導入をしました。そこで、タブレットというのは、子どもたちが興味をもって簡単に使えるのだと感じました。試験的にiPadを導入して授業で使ったときにアンケートの結果で子どもたちが何を求めているかというと、僕自身は工夫していろいろな教材を提供したのですが、子どもたちが一番便利だといったのは、自分のペースで学習できることだったようなんですね。例えばわからないところがあれば繰り返し聞くことであったり、わかっているところはスキップして進めることができるように、自分のペースで進められることが一番いいと示してくれたので、このまま一人一台で導入したらいいと思い、ICTについていろいろと取り組んでいきました。
一番ショックだったのは、中学の英語の授業で「Repeat after me.」と言って、コーラスで一斉に英語を読むときでした。子どもに「先生と一緒だとわからなくなると途中でやめたりしていたけど、タブレットでやると自分のペースで繰り返し学ぶことができるのでとてもよかった。」と言われました。その時に生徒にはそっちの方がいいんだなと感じたこともありました。
中村 僕がよく覚えているのは、中高で英語はまあまあできている方でした。でもそれはあくまでペーパーではできていた、というのが今でも感じることです。英語に興味があって関西外国語大学に進学し、その時にクラブとラジオのDJを始めて、英語でDJができる方が幅が広がると思い、アリゾナ州立大学に留学しました。その時の最初の授業でコミュニケーションクラスがありました。いきなり先生がテーマを出して、そのテーマについて学生がディスカッションし合うクラスだったんですね。その時のテーマがeuthanasia=安楽死で、僕自身聞いたこともなかったし考えたこともなかったんです。でも他の国の人達は、そのトピックに対して自分の考えを持ち、なぜなら~、賛成です・反対です、というやり取りをみんなが始めたのです。ただ、僕は何も言うことができなかったんですね。英語が得意だと思っていたのはあくまでもペーパーベースのものであって、実践的な英語の力は無いと感じました。その時にいろいろとルームメイトに助けてもらって生活には慣れていったんですけど、やっぱりそんな経験を日本の学生たちに味わってほしくないという思いから、実践的な英語教育を教えたいと思い、ECCで勤めることになりました。実際に授業実践もさせてもらいましたし、マネジメント業務もしていました。最終的には、西日本、東日本の責任者をさせてもらって、その時に感じたのは英語ができるといろいろな場面で役に立つということでした。そこからマネジメント業務中心だったのですが、ふとECCで勤める理由を思い出した時に、賢明学院からお話をいただいて、子どもたちに教えることになりました。自分自身、なぜ英語を教えることになったのかというと、子どもたちに将来役に立つ英語の力を身に着けてほしい思いがあり、ECCで働き始めたことを思い出して、現在に至ります。
司会 やっぱり一番のきっかけはアリゾナ州立大学での出来事だったんですね。
中村 自分が苦労してきたことは、子どもたちには味わってほしくないのと、後はECC時代に英語ができなくて困っている人をたくさん見てきて、また一流企業にいても実践的な英語力が全く身についていない人を見てきました。だからこそ、最初から実践的な英語力を身に着けてほしいと日々感じています。

子どもたちにつけてほしい力
反田 言葉を正しく使ってほしいですね。日本語でも英語でも、コミュニケーションのツールなので上手に使って、色んな人たちに自分の考えを伝えたり発信するとともに、国内のみならず海外の人ともコミュニケーションをとって自分の見識を深めてほしいです。深く考える力や自分の興味を持ったことをとことん極めていく力(探究心)も身に着けてほしいですね。そうでないと自分の考えも生まれてこないし、思考も生まれてこない。そうなると相手に伝えることも希薄になってしまいます。これはあらゆる物事の基本になると思いまして、言語を教えている教員としては一番願うことですね。
司会 言葉を大切に使ってほしいというのは国語科でも仰っていました。やっぱり言語は教科関係なく、重要になってくるのだと改めて感じました。
反田 言葉を正しく理解して、正しく使わないと知識が確実になっていきません。例えば書物を読んだりしたときに正しく読み取れるか、それをもとに自分が正しく考えを伝えられるか、ここで重要になってきますよね。日本語英語問わずにです。
中村 3歳から80歳までの年齢の方々に教えてきた経験から、今学校の中で考えると、どうしても日本には受験というものがあるので、私立文化の中で、実績を出すことは重要になってきます。そこに関してはまったく否定はありません。当然文法も必要ですし、単語も覚えないといけないし、読む力も必要です。そこから速読もしないといけないし、その前には精読も必要になってきます。アウトプットの前段階で受験指導は必要だと思います。ただ最近いい傾向だなと思うのは総合型選抜が増えてきたことです。個人で頑張ってきたことや自分が特化していることを論理的に説明できることが問われるのでいい傾向だと思います。また、自分の授業を通じて表現することに自信を持ってほしいです。なので、最初はおとなしかった子が授業を通じて、英語を間違えてもいいから話してみたいなと思う姿勢というのをつけていくことで人の前で話していく姿を見られるのはとてもうれしいことです。アウトプットの時間はたくさん使うんですけど、その次はサバイバル的な要素の学習の時間を設けています。本来は留学することが一番で、海外の方とたくさん話す機会があればと思っています。でも、今ではオンライン英会話があるし、他にも機会はありますよね。話すことによって、その国の文化や政治、教育等、深いところまで探求し、日本と海外を比べたらどうなのか、というところまで探求して、日本を改めて見つめ直すことも必要なんじゃないか思っています。ただ、英語だけできても仕方がないんです。なんか専門性がプラスでつかないと、職業も限られてくるし、結局身に着けたことを活用できる場面に制限がかかってきます。今では通訳や翻訳をしてくれるツールもあります。なので、専門性は必要だなと思いますね。
賢明学院小学校の児童の印象はどうですか
反田 何事に対してもとてもモチベーションが高くて、礼儀正しくてきちっとしているというのが第一印象です。朝には挨拶もしっかりしてくれますし、そういうところから気持ちよく一日がスタートできるモチベーションを僕自身がもらっています。また、お互いに対するリスペクトを感じます。それは先生に対してもクラスメイトに対しても、相手を大切にする姿勢を持っている印象があります。なので、毎日の授業の中でも気持ちがいいですね。
中村 授業外でも英語以外でも何事にも取り組む姿勢がとても前向きで、委員会とかクラブ活動や掃除でも、きちんと縦割りの面で高学年の子が意識をもって低学年と関わっていますね。世話好きであったり、優しい子が多いと思います。それはカトリック校としての教えの部分でもあります。
反田 始業式が終わって、新任に教員が紹介されて、教室に戻るときに担当する学年以外の5年生や6年生まで立ち止まって「よろしくお願いします!」と言ってくれたのが、とてもびっくりしました。ちゃんと紹介を聴いてくれていたんだという嬉しさと、先生への声掛けがとても気持ちがよかったんです。「先生よろしくお願いします!」という声掛けに、校内でこれから一緒に生活するからこその思いで言ってくれているんだろうと感じましたね。

英語科×AIの今後の可能性
中村 AIはこれまでも英語学習においてサポートツールとして注目されてきましたが、最も大切なのは単に情報を取得するだけで終わらせず、自分の頭に落とし込み、最終的に発信できる力を養うことです。授業はインプット2割・アウトプット8割を基本とし、放課後のオンライン英会話やAIチャットを活用してサバイバル的な対話を通じて実践力を強化しています。文部科学省の英語教育強化プロジェクトモデル校リーダーとして、30年以上の指導経験を日々アップデートしながら、教員同士や子どもたちとの双方向の学びを重視して、高校卒業時にはたとえ流暢でなくても自分の考えや伝えたいことを英語で相手に分かるように伝えられる発信力を到達目標とし、AIを含む多様なツールと実践を組み合わせてその育成を追求し続けたいと思います。
反田 もともと英語教育では以前から音声や映像に始まり、ICT(情報通信技術)との親和性はとても高いです。聴いて練習する発音練習ソフト(アプリ)や書いた英文をチェックしたり、英文作成(翻訳)アプリなど数多くあります。最近生成AIの進化がめざましく以前できなかったことが簡単にできるようになり、単語の発音のチェックができたり、英語、日本語の双方向で簡単に翻訳できるようになりました。このような時代を迎え「英語学習」「英語を習得すること」の意味が問われてきます。このような最新の技術を活用しながら、英語の言語能力を高め、人と人とのコミュニケーションを深めていくことが重要な視点であると思います。今の時代を生きる子どもたちには、AIをうまく活用しながら英語のスキルを高めていってほしいものです。(※生成AIの利用についてはそれぞれのAIの利用規約にもよりますが、基本的に13歳以上18歳未満が使用する場合、保護者の承諾が必要です。)

文部科学省「AIの活用による英語教育強化事業モデル校」
文部科学省による「小・中・高等学校を通じた英語教育強化事業(AIの活用による英語教育強化事業)」に採択された総合教育・生涯学習機関ECCが開発したシステムを、実際に実践して検証する実証事業の場として、賢明学院小学校が選ばれた。日本の英語教育を発展させるための事業に英語科主任のNaoki先生がプロジェクトリーダーとして、反田先生と文部科学省の取り組みに対し、力を発揮する。