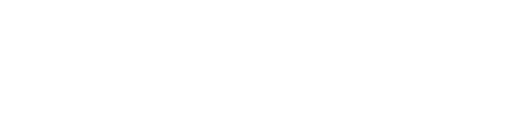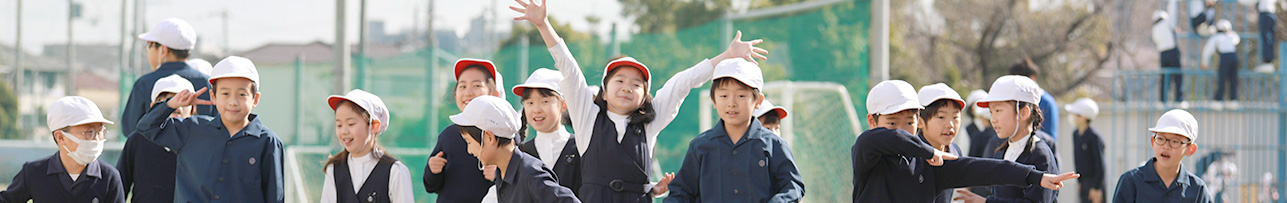お知らせ
2025/08/28
教師になったきっかけ
榎本 小学4年生頃から小学校の先生になりたい思いはありました。2年生から中学受験をするために大手進学塾に通うようになりました。関西学院でアメリカンフットボールをするために受験をするようになった感じですね。田舎の公立小学校だったので、中学受験をする人もほとんどいなかったのですが、担任の先生からたくさんのご協力があり、何とかご縁をいただきました。一人ひとりに寄り添ってくれる先生への憧れもあったり、担任の先生から「榎本は小学校の先生に絶対に向いていると思うよ!頑張れ!」と言っていただいたことから、小学校卒業時に決意が固まりました。結構、小学校ではやんちゃだったのですが…。
一番印象に残っていること
榎本 溝本先生と一緒でやっぱり54期生との出会いが一番ですね。何もかもが初めてで、毎日みんなと一緒に成長できたことはとても貴重な経験でした。毎年初めての授業・単元・行事・宿泊など、私にとっても子どもにとっても新しいことだらけなので、一緒に成長させてもらいました。子どもたちや先生方、保護者の方に感謝の思いでいっぱいで、この経験があってこそ今の自分があります。修学旅行や体育大会のことも今でも鮮明に覚えています。特に体育大会の演技に関しては、彼らとともに頑張ったからこそ、体育大会の演技を構成することに一層の熱が入るようになりました。子どもたちの達成感と無限大の可能性を感じたからこそだと思います。
溝本 がむしゃらでしたよね。本当に。とにかく必死になって「あぁでもない、こうでもない。」ってずっと悩んでいましたよね。そういえば、集団行動・組体操・フラッグを全部やったのが最後でしたよね。
阪井 最高学年での体育大会の成功って、最後の1年間を送る上でとても大切な機会だと思いますね。
榎本 体育大会は、学級経営という面でも重要な位置づけだと思っていますし、1年間を決める大きなものだと思っています。何をもって成功したかと定義づけするなら、たくさんの子たちが達成感を感じればいいなと。ではそのためには、「どういう声掛けをするべきか。」「どういう演技を構成するべきか。」などを常に考えていました。気づけば、毎年体育大会が終わった時に、「来年この学年の担任だったらこの曲で演技をしたいな。」と考えるようになっていました。
教師として大切にしていること
榎本 志で終わらず、有言実行することだと思います。子どもだけでなく他者に何かを求めるなら、自分が絶対にすることは昔から心がけています。だからこそ、上を目指さないといけないし、常にチャレンジ精神を持っています。僕っていつも一人で焦っている気がします。「子どもたちがこんなに頑張っているんだから、もっとしっかりやらないと。」とか「先生方もこんなに頑張っているんだから、僕も頑張らないと。」と常に考えているんです。
溝本 その姿を見て、周りも影響を受けているんで、ある意味いい刺激になっているんです。榎本先生はそこが絶対にぶれないから、何か言われても納得せざるを得ないです。私も子どもたちに言うんですけど、やっていない大人に言われても、「なんで言われなあかんの?」ってなるけど、先生の場合は納得できる。
阪井 言葉よりも行動で示すタイプよね。
榎本 素は出さないし、言葉にも絶対に出さないから、本当に面倒くさい性格だなと自分でも思っています。ただ、社会人としても教師としても行動では絶対に示さないといけないと思っています。
大切にしていることをどのようにして培ったか
榎本 子どもたちにいつも言うのは、「失敗してもいいからチャレンジしなさい。とにかくやってみよう!」です。これは10年間続けてきたアメリカンフットボールはもちろんですが、湊先生との出会いも大きいです。
ちょうど7年前、僕が初めて全国私立小学校連合会で研究発表をする機会がありました。たくさんの有名な先生方がいる前での発表に、さすがに緊張していました。教育って、正解はなく何事にも賛否両論がありますので、何を言われるだろう…とドキドキしていました。そして、57期生とチャレンジした授業を発表するときが近づいてきたときに湊先生が僕の肩をポンとたたいて「倒れるんやったら前やろ。」「大丈夫やから。こけたとしても前に倒れたら前進やねん。頑張っておいで。」と言葉をかけてくださりました。この言葉があってから、教師として何事にも思い切って挑戦できるようになったと思います。
阪井 じゃあ先生は今でも失敗していますか?
榎本 めちゃくちゃしていると思いますが、その失敗が楽しくて、チャレンジできていますし、たくさんの授業が生まれてきました。昨年から理科の担当をしていますが、60期生とチャレンジしたマグネシウムの燃焼実験もその一つです。彼らに特別な学びをしてほしい思いから生まれた授業で二酸化炭素内でも水中でも燃えるという彼らにとって今までの常識を覆すような授業をして、新しい学びをしてほしかったんです。今年だってそうです。何か61期生とチャレンジしようと思い、2学期と3学期に今までしたことがない実験や学習に取り組む予定です。僕のチャレンジから生まれるものはすべて子どもの未来につながるように、極限まで想定外をなくすよう授業準備をしています。

教師として大切にしていること
溝本 そこまで自分の考えとして身についたとても強い芯はどのようにして培われたのですか?
榎本 まだ現役でプレーしていた時の新聞記事に「関学のアメフトは、全員が納得してプレーをしているところに一番の強さがある。」と書かれていましたが、これに詰まっているかもしれません。アメフトやフラッグフットボールって、一人ひとりの役割がとても明確なのですね。流動的に役割が変わるわけではなく、基本的に役割は1つで、それを極めることを求められます。そして、1つのプレーの中で味方の11人が自分の役割を果たそうと一斉に動き出すんですね。その時に、プレーの中で全員が何をしているのかを確実に把握しておく必要があるし、味方の動きが分かっていなかったら全く動きがかみ合わずプレーが失敗します。だからこそ、チームメイトの動きだけでなく、日本一を目指す仲間として互いに目標とかも頭の中に入れて日々過ごしていました。
この経験は今でも生きています。担任していた時には「いつも目的意識をもって行動しなさい。」と言っています。一つ一つの言動にちゃんとした目的を持つことで、その言動に意味を持ちます。クラスの中であれば、それを追及していくと学級・学年目標に行きつくわけですね。
だから、僕はいつも個人の目標は後ろに掲示をして、全員が互いの目標を見られるようにしています。そして、学級委員には「できる限り全員の目標を覚えましょう。」と言っています。目標を書いて満足するのではなく、行動して成果が出るまで頑張ってほしいです。特に学級委員はプレッシャーだとは思いますが、みんなが乗り超えて成長していました。すごいなといつも感心しています。
阪井 アメフトって日本ではとてもマイナースポーツだけど、教師の生活やクラス作りと似ているよね。集団で何か達成しようとなれば、一人ひとりがしっかり勉強していないといけないし、理解していなければ何もうまくいかないよね。
溝本 チームスポーツはたくさんあるけど、ここまで一人ひとりの役割が違うっているのは珍しいですよね。ポジションの違いは多少あっても、ここまではっきり決まっているスポーツはないなと思います。
榎本 分かっているふりでは前進できないですよね。何事においても「知っている」と「理解している」は全然違いますから。賢明学院小学校の子どもたちはどの授業でも、分からないところがあったら堂々と手を挙げますし、友達同士で教えあう姿がいろんな場面で見られます。みんなで成長する環境が整っていますし、一人ひとりの個性を伸ばせる環境もあります。子どもたちの姿勢から私自身が学ぶこともたくさんあるくらいです。

強みと弱み
榎本 さっきもあったように強みは、決めたことは結果を出すまで取り組むことだと思います。有言実行と言っても行動を起こすだけで終わるのは、誰にだってできます。僕は教師である以上、常にその先を自分に求め続けています。
弱みは自分に自信を持てないことです。なかなか自信を持てない時が多くて、昔から本音はあまり出せない人間でした。だから、今まで話してきたことと矛盾しているところもたくさんあります。「何をどこまで求めて達成できたら、それを自信と呼んでいいのか?」と常に考えて、答えが出てこないまま30年が過ぎました。
溝本 榎本先生って、自分で何とかしないととか、人に気を使いすぎているかもしれませんね。
榎本 教師である前に大人として「この人なら何とかしてくれる。」と思われるような人でありたいと思っています。何か困ったときや逆境、大事な時にこそ頼られるような人間でありたいですね。アメフトをしていた時は、目指していたけれどそんな存在にはなれなかったので、教師として社会人として、そういう存在になりたいと強く思っています。そのためには、努力し続けないといけないですね。
溝本 求められるってとても大事だと思います。クラスでもそうですけど、求められることは一番の原動力になると思っています。
賢明学院小学校の大好きなところ
榎本 昨年度より管理職になって今までと違った目線で、賢明学院小学校を俯瞰するようになりました。今までは、担任していたクラス・学年を中心に俯瞰していましたが、こうして改めて全体を見てみると「素敵」な部分がたくさん見られました。先生方にも子どもたちにも保護者の方にも共通するのが「Empathy(共感)」を大切にしていることだと強く思います。それを一番強く感じるのは、先生方や高学年、保護者の方が低学年と話している時に、しゃがんで同じ目線になって笑顔で話している時です。授業の時、休み時間の時、掃除の時、登下校の送り迎えの時、様々な場面で見かけていて、とても幸せな気持ちになります。こうした環境は、低学年にとって安心感があっていろいろなことに挑戦できる勇気が湧いてくるのだと思います。だから賢明の子たちは、強いハートを持っていますし、ある意味恐れ知らずというか、どんな大舞台での挑戦もすべて前向きです。
教員の中でも具体的なEmpathyを感じるときがあります。それは、常に担任団や先生方との対話を大切にして、子どもたちや小学校のために100点ではなく130点の成果を出すところです。こうした環境があるからこそ、教員も子どもたちも思い切って挑戦できるのだと思います。個人的に一番好きなところです。
賢明学院小学校の子どもたちに伝えたいこと
榎本 自信を持って自己紹介ができる人になってほしいですね。自己紹介って、「〇〇が好きです。」とか「趣味は〇〇です。」といったような自己紹介ではなく、たくさんの経験をもとに「私はこんな人間だ!」と胸張って言ってほしいです。54期生から始めた振り返りノートの目的は、まさにここにあります。
もう一つありまして、それは好きなことをとことん夢中になってやり切ってほしいということです。例えば、音楽が好きだとか、バスケが好き、英語が好きなど、誰にだって夢中になっているものはあると思います。でも、それにとことん打ち込んでいると、ある日突然いやになってくるときがたまにあるんです。特に多いのは、うまくいかなくなったときですよね。思い通りにならないこともありますし、結果が思うように出なくなる時もあります。そういう時こそ、乗り越えて続けてほしいなと思いますね。大抵の人は、好きじゃなくなった瞬間にやめてしまいます。でもそういう時こそ、好きで夢中になり始めた瞬間を思い出してほしいのですね。乗り越えた時こそ、一気に成長できて極めていくきっかけになります。とにかく自分が納得いくまで追求してほしいです。
自分の未来は自分で作らないといけませんから。

榎本 裕司 教頭補佐
関西学院大学教育学部卒業。在学中はアメリカンフットボール部に所属し、全国制覇3連覇を達成。2014年4月より賢明学院小学校に勤務し、担任、学年主任、算数科・体育科の専科教員を経て、2024年度より教頭補佐に着任。現在は、教科・教科外指導および研究の統括、理科主任、進路指導部長を務める。大阪府私立小学校連合の算数部会・学級経営部会の幹事として、全国・西日本・東京都・大阪府において研究発表を行う。2019年からは、関西学院大学教育学部にて教職実践演習の講師を務める。数学教育学会に所属し、主にデータの活用領域に関する論文を執筆。
数学教育学会 所属
関西学院大学教育学部 教職実践演習 講師(2019~)
大阪府私立小学校連合 算数部会 幹事(2020~2023)
大阪府私立小学校連合 学級経営部会 幹事(2024)