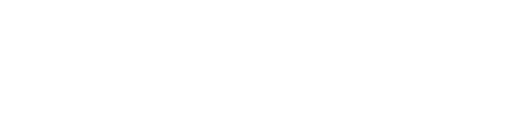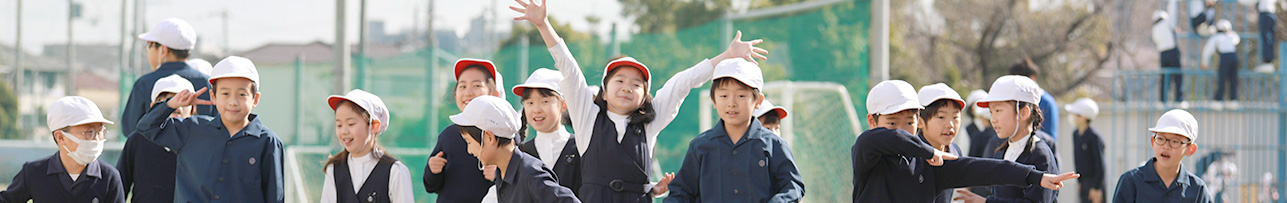お知らせ
2025/09/03
最後は谷口校長先生のトークセッションです。
本校の教育について、校長先生から見た良さを語ってもらいました。
是非ご覧ください。
谷口 晋哉 校長
千葉大学教育学部卒業後、兵庫県教育委員会に採用され、兵庫県西宮市立小学校教諭として20年間勤務。その間、在外教育施設派遣教員としてパラグアイ共和国アスンシオン日本人学校に3年間派遣される。その後西宮市教育委員会に指導主事、係長として8年間勤務。西宮市立小学校の教頭として3年間勤務後、西宮市教育委員会教育研修課長を務める。2016年4月より6年間、西宮市立高木小学校長、内2年間は西宮市立小学校長会長を務める。2023年4月賢明学院小学校校長に着任、現在に至る。兵庫県教育功労者表彰受賞。
教師になったきっかけ
私が教員を志した理由は、一言でいえば「出会いの積み重ね」です。小学校や中学校で過ごした日々の中で、直接関わってくださった先生方の姿勢や温かさに触れ、それが自然と自分の将来像の一部になっていきました。特に、小学校1年生のときの担任の先生のことは今でも鮮明に覚えています。腰の低い、丁寧で、子どもの一言一言を大切にする方でした。当時、低学年の担任がこれほど印象に残るというのは珍しかったと思います。
もっとも、私は常に「先生になりたい」と強く思い続けていたわけではありません。中高生のころには、建築家を目指したいと考えたこともあります。ただ、進路選択の時期に差し掛かったとき、迷いながらも最終的には教育学部への進学を決意しました。それは、子ども時代に出会った恩師たちの影響が、自分の中で確かな「芯」になっていたからだと思います。
私が大学生だった頃から10年ほどは、教師の採用枠が今より少なく、「なりたくてもなれない時代」が続きました。その一方で、さらに昔には「誰でも教員になれる時代」もあったと聞きます。そんな環境の中で、私が出会った先生方は、子どもを育てることに強い情熱を持っていました。その姿を見て、「自分もこんな大人になりたい」と自然に思うようになったのです。
海外派遣とパラグアイでの生活
教員生活が10年を迎えたころ、新しい環境で自分を試したい、視野を広げたいという思いが強くなりました。そんな折、中学校時代の恩師が海外の日本人学校で教えていたことを思い出しました。その先生から聞いた体験談が私の背中を押し、日本人学校の派遣に挑戦することを決めたのです。
派遣先は自分で選べず、任命されたのは南米パラグアイの首都アスンシオン日本人学校。当時の私はその国のことはほとんど知らず、ましてや首都の名前は聞いたことすらありませんでした。勤務していた学校の教頭先生と一緒に図書館に走り、地図を広げ、「ここか、南米か」と驚いたことを覚えています。
当時2歳の長男と妻を連れて渡航し、現地で長女が生まれました。長男は現地の私立幼稚園に通い、生活の中で自然にスペイン語を身につけました。帰国前には親の通訳までしてくれるほどでしたが、日本に戻って必要性がなくなると、あっという間に話さなくなり、忘れてしまいました。この出来事から、子どもの言語習得は環境に大きく左右されること、そして必要性がなくなれば驚くほど早く失われることを実感しました。
派遣先の学校は全校児童生徒17人。小学校教員は私を含め2名で、私は1・2年生を担当しました。少人数ゆえ、子ども一人ひとりと深く関われる「本当の教育」ができたと感じています。保護者の教育意識も非常に高く、家庭と学校が一体となって子供を育てる環境が整っていました。作文や発表などの力が目に見えて伸びる姿を目の当たりにし、教育の可能性を改めて感じる3年間でした。
昔と今の教育の違いをどう感じておられますか
私が教員になった頃は週6日制で、土曜午前中も授業がありました。午後は子どもたちと野球をしたり、一緒に地域の行事に参加したりすることもありました。授業は教師が一方的に話すスタイルが主流で、全員を同じ水準まで引き上げることが重視されていました。個性を生かす指導も存在しましたが、あくまで少数派だったと感じます。
それが今では、社会や技術の変化により、求められる力が大きく変わりました。AIが計算や情報処理を担える時代だからこそ、人間にしかできない創造、表現、発信が必要です。結果ではなく思考過程を重視し、試行錯誤を通じて新しい価値を生み出す学びが求められています。
賢明学院小学校の魅力
本校の大きな特徴は、カトリック精神が教育の根幹に息づいていることです。「祈り、学び、奉仕」という理念が学校全体に浸透し、子どもたちの生活や態度に自然に表れています。
在籍する子どもたちは、各ご家庭で愛情深く育てられた子が多く、「自分や他者を大切にする心」を持っています。笑顔が多く、落ち着きがあり、優しさにも独特の質があります。公立校にも優しい子はたくさんいますが、その根底にある価値観や育ちの背景が少し異なっているように感じます。
授業の様子を見ていても、教師が一方的に教え込むスタイルではなく、課題に対して子供たち同士が意見を交換し学び合う姿が見られます。互いを認めながら意見を交換し高め合っています。この授業スタイルは、高学年になるほど顕著に表れています。学びの過程を大切にしているとも言えます。
言葉を大切にする図書教育や英語教育にも魅力を感じています。高学年の英語は、話したい表現したいという子どもたちの気持ちが前面に出た、活気あふれる授業が展開されています。
子どもたちの成長過程で本物に触れる体験活動も多く準備され、人と人との関わりの中で、子どもたち一人ひとりの育ち、そして「わたしらしく」成長する姿が目に見える学校と言えると思います。
これからの時代における小学校の存在意義
AIは過去のデータを元に未来を予測することは瞬時にできますが、データのない全く新しいものを0から作り出すこと、新しいものを創造することはできません。また、相手の気持ちをくみ取るということもできません。
つまり、互いに言葉を交わし、コミュニケーションの力で、心の通じたやり取りができ、全く新しい知や価値を作り出すことができるのは、人間だけです。どんなに科学技術が発達し、世の中が便利になり、それまで人がしてきたことや仕事をAIやロボットが肩代わりするようになったとしても、人にしかできないことは必ずあるはずです。人が人としての力、人間力を磨き続けることが求められます。
AI時代になっても、小学校教師は代替されにくい職業だと言われます。それは、学校が子どもたちに学力・体力・感性の3つを、集団生活を通して育む場だからです。つまり、学校は人間力の基礎を育む場です。
学びの力を鍛え、体を動かし、心を磨く。これらは単に知識や技術だけではなく、人としての土台を築く営みです。教室という小さな社会の中で、互いに学び合い、助け合い、時にぶつかり合いながら成長する。その積み重ねが、将来の自立につながります。
だからこそ、小学校はこれからも変わらず必要とされますし、その使命を果たすために私たちは教育の質を磨き続けなければなりません。