お知らせ
2025/02/11
2025年1月29日水曜日の午後、賢明学院高校3年生AP授業の生徒たちによる第3回AP成果発表会がリヴィエホール・アリーナにおいて、同級生、在校生、教員、保護者など多くの人を集めて開催されました。

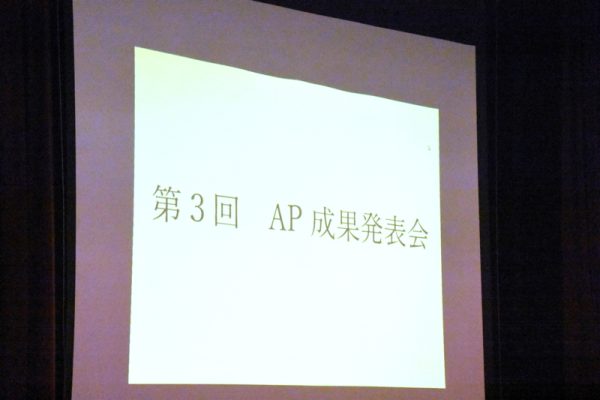
関西学院大学理系4学部への特別入試を終え、20名の合格通知書を手にした後のことでした。
前半では生物環境研究室から3グループ、数理物理学研究室から3グループの6グループが、後半では建築研究室から3グループ、工学研究室から3グループの6グループ、合計12グループが成果発表を行いました。
グループで協力して発表したところやひとりで発表したところもありましたが、どれも大変聞きごたえのあるものでした。







関西学院大学理系学部との提携が結ばれ、同時にこの賢明学院KGSSC創設とともにAP授業が始められました。第1期生、第2期生からのバトンを引き継ぎ、先行研究を基とした、また新たな観点に課題を見つけて取り組んだのもありましたが、AP授業を継続させた努力に敬意を表します。まずは「何を問うのか」のテーマを定めるまでに、先行研究や関連した事柄を随分時間をかけて調査しながら研究課題を設定するのに大変苦労したことと思います。与えられた問題に対して解答していくのではない難しさがそこにはあります。「答え合わせ」ではなく、「自らの答え」を見出していく、ここにサイエンスの面白さがあります。受講する生徒たちとそれを導く教員たちが作り上げていったAP授業の成果をみんなの前で披露伝達できたことは本当に有意義なことでした。








発明王 トーマス・エジソンは1847年 2月11日、アメリカ、オハイオ州ミランで、父親サミュエル・オグデン・ジュニアと母ナンシー・エリオットの間に、7人兄弟の末っ子として誕生しました。彼は小学校にはなじめずに学校ではなく母親から色々なことを学んでいます。後に偉大な発明王と呼ばれるのですが、母親の教育方針は正しかったと言えましょう。
そのエジソンが残した言葉に次のようなものがあります。
I have not failed. I’ve just found 10,000 way that won’t work.
私は失敗したことがない。ただ、一万通りの、うまくいかない方法を見つけただけだ。
定期考査や入学試験のように正しい解答をひたすら追求する、無駄なことはしないという中で、この言葉は非常に重みを持っていると感じます。答えのあるもの、そのような問いかけにはこれからはAIが人間よりはるかに早く、正確に答えを導き出していくでしょう。しかし、「やってみないと分からないこと」があるのです。そして自然科学はまさにこれの宝庫なのです。「無駄なことは一切しない」では新しいことの発見は望むべくはありません。やってみる前から「無駄だ」と躊躇してしまうのでは進歩は望めません。そもそも「無駄」なことって実際にはどのようなことなのでしょうか。私には「やらない言い訳」にすぎないように思えるのです。今回発表してくれた皆さんがそのことをしっかりと伝えてくれました。「探究」の面白さと神髄をみせてくれたことにとても嬉しく思います。



審査委員の一人を務めましたが、分野が違えば発表の内容も大きく違い、採点の甲乙もつけがたく大変苦労しました。その中でも全審査員の評価が特に高かった3グループに最優秀、優秀賞が授与されました。


最優秀に選ばれたのは工学研究室の太田優音さんと吉崎真帆さんが発表した「マッチング処理を用いたドローンの自動操縦の研究」でした。Pythonによるマッチング処理を基にしてドローンの自動操縦プログラムを開発し、標識を認識してドローンを飛行することを実現させました。発表態度も堂々としていた素晴らしい発表でした。
優秀賞にはこれに続く2グループが本当に僅差で選ばれました。一つは建築研究室の大口実来さん、浜名静さん、和田まといさんの「藁の家による耐風性能」でした。藁と糸のみを使用して、直方体、切妻型、テント型の建築模型を製作し、角度を変えた風を当ててその影響を調べた研究です。実験値をわかりやすく、また客観的に考察して非常に説得力のある発表でした。


もう一つは工学研究室の濱崎青空君、西山将睴君、益田巧貴君の「ドローンを用いた物体の運搬 ~艦隊飛行を用いた効率化~」でした。免許が不必要の小型ドローンを4台使用して、より重量のある物体を運ぶ研究です。ドローンを複数制御するシステムや安定し、より強度の高い運搬板の工夫などアイデアがいたるところに散りばめられた発表でした。表彰されたこれらの3つはまさにエジソンの名言を実践してくれた内容でした。


表彰された3グループ以外もそれぞれ面白い興味ある発表を聞かせてくれ、2時間以上に及ぶ発表会でしたが、最後までわくわくしながら聞かせてもらうことができました。忘れてはならないのはこの発表に至るまで様々な努力があったことです。
数理物理学研究室では、テーマとした数式を使いこなすには通常授業で履修した数学の領域を超えて微積分学を学び、微分方程式を導入できるように努力したり、ガウス整数を用いて数理ゲームの解析をするなど高校レベルを一歩超えた発表をしてくれました。

生物環境研究室では生き物を扱う難しさを伝えながら、子どもの頃の疑問やロマンある問い掛けに対する試みを実践してくれました。

それぞれのグループがあの6分の発表に籠められた思いは本当に大きかったと想像しています。
ここに総まとめとして第3期生の論文集を刊行することができ、大変嬉しく思います。KGSSC3期生の皆さん、本当によくがんばりました。
発表を聞いていた在校生には中学生も含まれていましたが、普段勉強している教科が基礎となっていることにあらためて気がついたものと思います。それは数学や理科だけでなく、発表するには国語や英語、製作するには美術や技術家庭などあらゆる教科がその土台となっているのです。単にテストのため、入試のためにとどまらず、その先をみせてくれた発表者の皆さんに心から敬意を表します。
「失敗ではなく、うまくいかない方法を見つけた」とのエジソンの言葉は、自然科学だけでなく人生を歩む上でも大事にしたいことです。これから歩む一人一人の人生において、この言葉を胸にして堂々と様々なことに挑戦していってください。最後になりましたが、このAP授業を導き構築させてくださったAP担当の先生方に心から厚く感謝申し上げます。3年間積み上げてきたこの賢明でのAP授業の取組が、「探究の賢明」と呼ばれるように賢明学院での新たな伝統へと成長していくことを心から願っています。

中学高等学校校長 石森圭一



